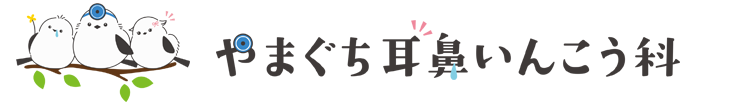尿検査
尿検査とは
尿検査とは、尿中の蛋白や糖などを調べ、様々な病気やその兆候を知ることができる検査です。
当院では尿に試験紙を浸して行う尿定性検査行います。主に蛋白、糖、潜血(赤血球)がどのくらい尿中に排泄されているか、試験紙の色調の変化により判定します。
当院では尿に試験紙を浸して行う尿定性検査行います。主に蛋白、糖、潜血(赤血球)がどのくらい尿中に排泄されているか、試験紙の色調の変化により判定します。

検査項目
当院では、ビジュアルリーダーIIと体外診断用医薬品U-テストビジュアル10を使用します。
検査項目は、pH、蛋白、ブドウ糖、ケトン体、ビリルビン、潜血、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、白血球、比重があります。
検査項目は、pH、蛋白、ブドウ糖、ケトン体、ビリルビン、潜血、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、白血球、比重があります。
耳鼻咽喉科で尿検査?
耳鼻咽喉科領域で特に重要であるのは、溶連菌による糸球体腎炎があります。耳鼻咽喉科や小児科では、溶連菌による急性扁桃炎の患者さんをたくさん診察します。溶連菌に感染すると溶連菌を排除しようと体の中に抗体ができます。この抗体が溶連菌に付着したものが腎臓で炎症を起こす病気です。
溶連菌と診断されたら、2週間後に尿検査を行います。尿検査で血尿や蛋白尿がみられれば腎炎と診断されます(高血圧も三主徴の1つです)。ただ、のどの感染の1~3週間後、皮膚の感染の3~6週間後に腎炎になることが多いです。そのため2週間後の検査では正常でも、その後におしっこの量が減って、むくみがでたり、褐色(赤色)の尿がみられた場合は、必ず受診してください。
そのほか、耳鼻咽喉科とは直接は関係なくても判明することができるものとして、蛋白で腎疾患、ブドウ糖で糖尿病・甲状腺機能亢進症、潜血で腎疾患・尿路結石・膀胱炎、ケトン体で重症糖尿病・嘔吐、ウロビリノーゲンで肝疾患、白血球で尿路感染症などがあります。
耳鼻咽喉科でも全身の病態を考えなくては診断ができないこともありますので、院長の考えとして当院では尿検査を導入しています。
溶連菌と診断されたら、2週間後に尿検査を行います。尿検査で血尿や蛋白尿がみられれば腎炎と診断されます(高血圧も三主徴の1つです)。ただ、のどの感染の1~3週間後、皮膚の感染の3~6週間後に腎炎になることが多いです。そのため2週間後の検査では正常でも、その後におしっこの量が減って、むくみがでたり、褐色(赤色)の尿がみられた場合は、必ず受診してください。
そのほか、耳鼻咽喉科とは直接は関係なくても判明することができるものとして、蛋白で腎疾患、ブドウ糖で糖尿病・甲状腺機能亢進症、潜血で腎疾患・尿路結石・膀胱炎、ケトン体で重症糖尿病・嘔吐、ウロビリノーゲンで肝疾患、白血球で尿路感染症などがあります。
耳鼻咽喉科でも全身の病態を考えなくては診断ができないこともありますので、院長の考えとして当院では尿検査を導入しています。