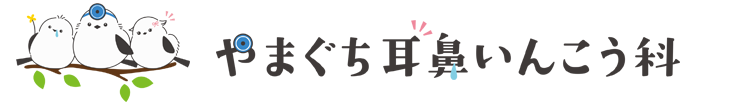発熱の診療
一般的に風邪をひくと、耳が痛くなる、鼻水で出る、のどが痛くなるなどの症状が現れます。
それらの症状が特に気になる場合は、耳鼻咽喉科の受診がお勧めです。
それらの症状が特に気になる場合は、耳鼻咽喉科の受診がお勧めです。
ページ内目次
インフルエンザウイルス
インフルエンザとは
インフルエンザウイルスに感染して起こる感染症です 。主にヒトに流行を起こすのは、A型とB型のインフルエンザウイルスです。
A型、B型インフルエンザの流行には通常、季節性があり、国内では例年12月~3月に流行し、短期間で多くの人に感染が拡がります。厚生労働省によると、例年の季節性インフルエンザの感染者数は、国内で推定約1,000万人とさえいわれています。
A型、B型インフルエンザの流行には通常、季節性があり、国内では例年12月~3月に流行し、短期間で多くの人に感染が拡がります。厚生労働省によると、例年の季節性インフルエンザの感染者数は、国内で推定約1,000万人とさえいわれています。
症状
通常 1~3 日間ほどの潜伏期間の後、38℃以上の発熱・頭痛・全身の倦怠感・筋関節痛などが突然現われ、咳・鼻汁などの上気道炎症状がこれに続きます。
合併症として、高齢者では肺炎・気管支炎を起こしやすく、小児では中耳炎や気管支喘息を誘発することもあります。
合併症として、高齢者では肺炎・気管支炎を起こしやすく、小児では中耳炎や気管支喘息を誘発することもあります。
インフルエンザと風邪の違い
症状として、普通の風邪のようなのどの痛み、鼻汁、咳などの症状もみられますが、38℃以上の高熱、頭痛、全身の倦怠感、筋関節痛などが比較的急速に同時に現れる特徴があります 。
また、小児ではまれに急性脳症を、高齢者や免疫力の低下している人では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。
また、小児ではまれに急性脳症を、高齢者や免疫力の低下している人では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。
インフルエンザが重症化しやすい方
- 5歳未満(特に2歳未満)のおこさん
- 65歳以上の方(特に呼吸器疾患や循環器疾患の既往のある方)
- 妊娠中、または産後の方
- アスピリンを服薬中の方
- 高度の肥満の方
検査
鼻やのどの粘液を綿棒でぬぐった液や、鼻水を迅速抗原検出キットで検査します。ウイルスの型まで短時間でわかります。
ただし、症状が出る前のウイルス量が少ない時期に検査した場合や、検査する材料の採取がうまくいかなかった場合は、感染していても陽性にならないことがあるので、注意が必要です。
ただし、症状が出る前のウイルス量が少ない時期に検査した場合や、検査する材料の採取がうまくいかなかった場合は、感染していても陽性にならないことがあるので、注意が必要です。
治療
発症から48時間以内であれば、抗インフルエンザウイルス薬を使用します。抗インフルエンザウイルス薬は、ウイルスの増殖を抑えて、発熱などの症状が消えるのを早めたり、体外に排出されるウイルスの量を減らしたりする効果があります。抗インフルエンザウイルス薬には、内服薬や吸入薬、注射薬もあり、それぞれ用法・用量が違います。予防のための投薬方法もあり、医師に確認しましょう。
症状を和らげる治療として、解熱剤、鎮咳薬、去痰薬などの対症療法が使われます。
からだを温かく安静に保つことで免疫力を高めたり、水分をこまめにとることで脱水状態になるのを防ぐことも重要です。
症状を和らげる治療として、解熱剤、鎮咳薬、去痰薬などの対症療法が使われます。
からだを温かく安静に保つことで免疫力を高めたり、水分をこまめにとることで脱水状態になるのを防ぐことも重要です。
インフルエンザ脳症について
インフルエンザを発症した後に発症する重度の中枢神経症状をともなう急性脳症のことです。特におこさんに多いです。
インフルエンザの症状に加えて、意識障害(呼びかけに反応しないなど)、意味不明の言動、けいれんといった症状があらわれます。このような症状がみられたら、速やかに医療機関を受診してください。また解熱剤によっては、インフルエンザ脳症を起こしやすくすることがあるため、ロキソニンなどの大人が使用する解熱剤の使用は、医師に相談してください。
インフルエンザの症状に加えて、意識障害(呼びかけに反応しないなど)、意味不明の言動、けいれんといった症状があらわれます。このような症状がみられたら、速やかに医療機関を受診してください。また解熱剤によっては、インフルエンザ脳症を起こしやすくすることがあるため、ロキソニンなどの大人が使用する解熱剤の使用は、医師に相談してください。
出席停止・通勤停止について
【おこさんの場合】
学校保健安全法施行規則第19条において、学校や園への出席停止の期間の目安は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」となっています。
また、出席停止の期間は、各学校や園によってそれぞれに定められている場合もありますので、確認してください。
【大人の場合】
大人には、インフルエンザと診断されてからの出勤再開に関して特に決まりはありません。しかし、一般的にインフルエンザ発症後7日目でも鼻やのどからウイルスを排出している可能性があるため、たとえ発熱等の症状がなくなっていても他の人にうつすことはあるので外出には注意が必要です。
基本的に、発熱がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。しかし、完全に他の人にうつさなくなる時期はあきらかではないため、注意してください。
学校保健安全法施行規則第19条において、学校や園への出席停止の期間の目安は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」となっています。
また、出席停止の期間は、各学校や園によってそれぞれに定められている場合もありますので、確認してください。
【大人の場合】
大人には、インフルエンザと診断されてからの出勤再開に関して特に決まりはありません。しかし、一般的にインフルエンザ発症後7日目でも鼻やのどからウイルスを排出している可能性があるため、たとえ発熱等の症状がなくなっていても他の人にうつすことはあるので外出には注意が必要です。
基本的に、発熱がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。しかし、完全に他の人にうつさなくなる時期はあきらかではないため、注意してください。
予防
予防接種でインフルエンザウイルスの感染を完全に予防することはできませんが、インフルエンザにかかる人や、重症化する人を減らすことができます。
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンです。インフルエンザウイルスの感染力を失わせて人が免疫を作るのに必要な成分だけを取り出して作ったものです。勘違いされている方も多いのですが、インフルエンザワクチンには感染力がないので、予防接種によってインフルエンザを発症することはありません。
インフルエンザワクチンは、13歳未満では2回接種で、13歳以上では原則1回接種です。しかし、患者さんの状況等によって医師の判断により2回接種が勧められる場合があります。
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンです。インフルエンザウイルスの感染力を失わせて人が免疫を作るのに必要な成分だけを取り出して作ったものです。勘違いされている方も多いのですが、インフルエンザワクチンには感染力がないので、予防接種によってインフルエンザを発症することはありません。
インフルエンザワクチンは、13歳未満では2回接種で、13歳以上では原則1回接種です。しかし、患者さんの状況等によって医師の判断により2回接種が勧められる場合があります。
フルミスト点鼻薬について
痛くないワクチンとして、2023年3月から鼻からスプレーで注入するインフルエンザワクチン「フルミスト点鼻薬」があります。従来のインフルエンザワクチンと同等な効果があるとされています。
従来の不活化ワクチンとは違い、ウイルス自体を弱めて使用した生ワクチンです。ほかの予防接種との間隔が必要なことがあります。2歳から18歳までが対象です。
メリット
デメリット
従来のインフルエンザワクチンにするか、フルミスト点鼻薬にするか、判断に迷われる方は医師と相談しましょう
従来の不活化ワクチンとは違い、ウイルス自体を弱めて使用した生ワクチンです。ほかの予防接種との間隔が必要なことがあります。2歳から18歳までが対象です。
メリット
- 痛みがない
- 年齢に関係がなく、1回の接種で良い
- 従来のインフルエンザワクチンと同等とされている
デメリット
- 8000円前後と値段が高い
- 2歳未満のおこさんは適応外
- 妊娠中または授乳中の方(妊娠可能な女性においては避妊が必要)
- 喘息や慢性呼吸器疾患のある方(特に過去1年以内に喘息の発作をおこした方)
従来のインフルエンザワクチンにするか、フルミスト点鼻薬にするか、判断に迷われる方は医師と相談しましょう
咳エチケット
咳やくしゃみに含まれている病原体が、周囲に飛び散らないようにすることが重要です。咳やくしゃみをするときは、周囲の人の方は向かず、ティシュなどで口と鼻を覆います。咳、くしゃみが出ている間はマスクを必ず着用してください。

厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
マイコプラズマ
マイコプラズマ肺炎とは
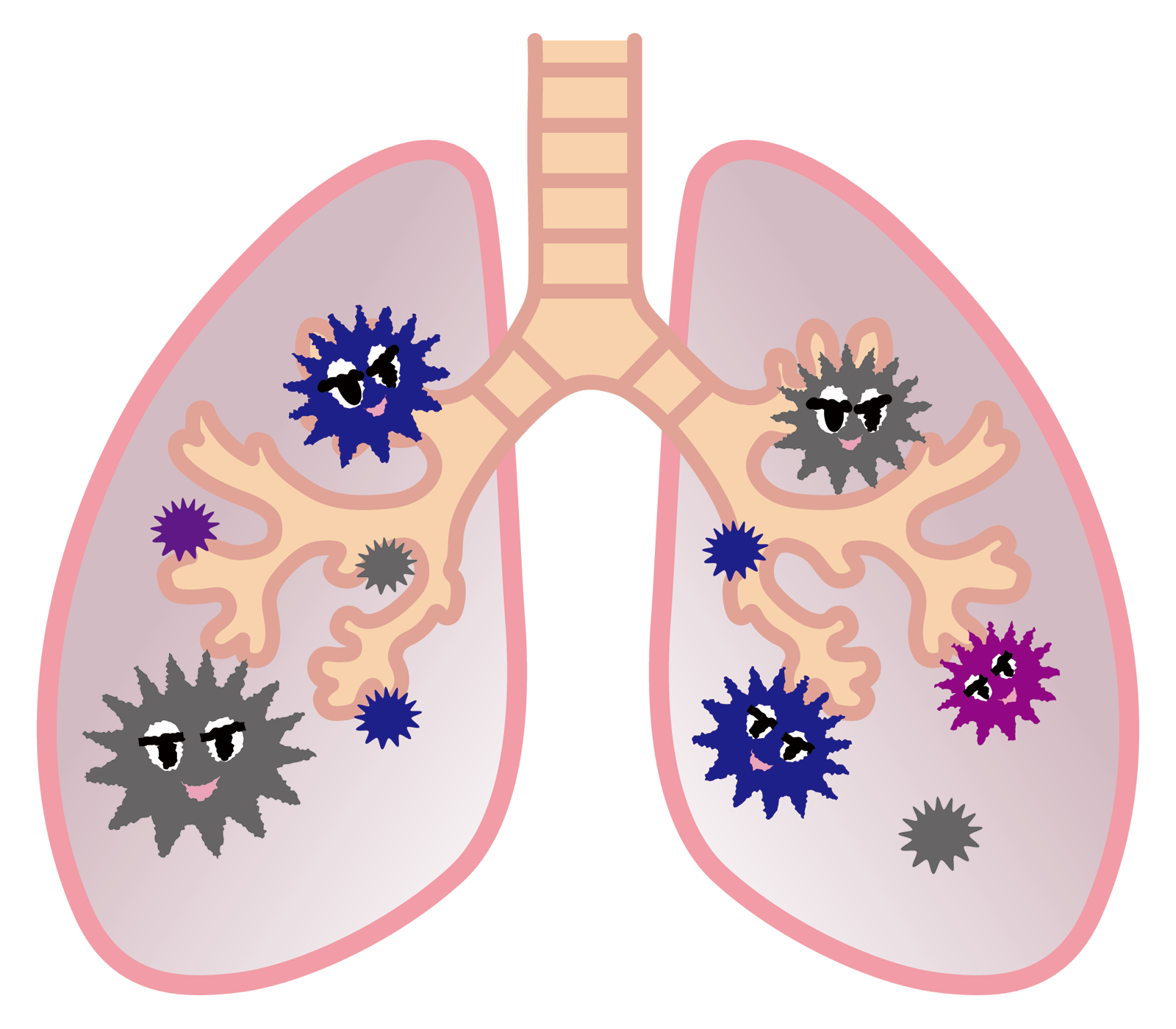
マイコプラズマは、風邪症状、気管支炎や肺炎を起こす細菌の一種です。
細菌に分類されますが、マイコプラズマは一般の細菌とは構造が異なり細胞壁をもたないため、他の一般細菌とは区別され、効果のある抗菌薬も限られるのが特徴です。
マイクプラズマ肺炎は、マイコプラズマと呼ばれる細菌の一種に感染することによって引き起こされる肺炎のことです。マイコプラズマ感染症全体の3~5%程度と言われています。
小児や若い世代に比較的よく見られる肺炎であり、発症者の約8割は14歳以下であるとされています。
細菌に分類されますが、マイコプラズマは一般の細菌とは構造が異なり細胞壁をもたないため、他の一般細菌とは区別され、効果のある抗菌薬も限られるのが特徴です。
マイクプラズマ肺炎は、マイコプラズマと呼ばれる細菌の一種に感染することによって引き起こされる肺炎のことです。マイコプラズマ感染症全体の3~5%程度と言われています。
小児や若い世代に比較的よく見られる肺炎であり、発症者の約8割は14歳以下であるとされています。
原因
マイコプラズマは、病原体が含まれた感染者の咳やくしゃみを吸い込んでしまう飛沫感染と、病原体が付着した物に触れ、その手で鼻や口を触ることによって体内に病原体を取り入れてしまう接触感染によって感染が広がっていきます。
いずれも周囲に感染者がいると感染するリスクが高くなり、特に小児の集団生活の場で感染が広まることが多いです。
マイコプラズマ肺炎は冬に感染者がやや増えるものの、1年を通して発症する可能性があるため、注意が必要です。
いずれも周囲に感染者がいると感染するリスクが高くなり、特に小児の集団生活の場で感染が広まることが多いです。
マイコプラズマ肺炎は冬に感染者がやや増えるものの、1年を通して発症する可能性があるため、注意が必要です。
症状
マイコプラズマ感染症の多くは、マイコプラズマに感染して2~3週間の潜伏期間を経た後に、一般的な風邪症状(発熱、倦怠感、咳、頭痛、腹痛など)で、約1週間程度で治癒します。そのため、最初は通常の風邪と判断がつきません。
マイコプラズマ肺炎になるのは、マイコプラズマ感染者全体の3~5%程度と言われています。マイコプラズマ肺炎の症状には、「乾いた咳がなかなか治らない」「熱が下がらない」という特徴があります。
はじめは痰の絡まない乾いた咳であることが多いですが、その後痰を伴い、気管支炎や肺炎に至ると、3~4週間としつこく頑固な咳に変わります。
重症化した場合は、苦しそうな呼吸も見られます。重症化した場合は注意が必要です。
そのほかにも、胸の痛み、のどの痛み、声のかすれ、下痢・嘔吐、皮疹など多岐にわたる症状も引き起こします。
マイコプラズマ肺炎になるのは、マイコプラズマ感染者全体の3~5%程度と言われています。マイコプラズマ肺炎の症状には、「乾いた咳がなかなか治らない」「熱が下がらない」という特徴があります。
はじめは痰の絡まない乾いた咳であることが多いですが、その後痰を伴い、気管支炎や肺炎に至ると、3~4週間としつこく頑固な咳に変わります。
重症化した場合は、苦しそうな呼吸も見られます。重症化した場合は注意が必要です。
そのほかにも、胸の痛み、のどの痛み、声のかすれ、下痢・嘔吐、皮疹など多岐にわたる症状も引き起こします。
診断
マイコプラズマ抗原定性検査
咽頭をスワブで拭って抗原を検出する方法です。咽頭で検査をしますが、当然肺や気管支からは距離があるため、咳がひどくない状態では検査はすすめられません。一般的に感度は50%程度と低いです。陽性的中率は90%です。つまり、マイコプラズマに感染していても陰性と出ることが比較的多いですが、陽性であればマイコプラズマと判断して問題ないです。
検査判明が15分程度で結果が出るため、当院でも積極的に行います。
検査判明が15分程度で結果が出るため、当院でも積極的に行います。
LAMP法(遺伝子増幅法)
LAMP法(遺伝子増幅法)といって、マイコプラズマのDNAを調べる検査方法です。感染初期から検出可能な方法ですが、結果がでるのに3日程度かかります。
血液検査
血液を採取し、血清中の抗体を調べる方法もあります。しかし、抗体は感染初期にすぐには産生されないため、初期の診断には向かないことと、より正確に判定するにはペア血清(感染初期と、2~4週間してからの2回採血を行い比較します)による抗体価の上昇を確認する必要があります。診断に時間を要するため、クリニックなどでの日常診療の場ではあまり使い勝手の良い検査ではありません。
マイコプラズマは気管支や肺で増殖して、肺炎をおこします。咽頭をぬぐって検体をとる場合、菌が喀痰とともに気管支から咽頭付近まで排出されてこないと、検査で検出することができません。つまり、感染していたとしても、必ずしも検査で検出されるわけではなく、マイコプラズマ感染症の診断は難しいケースが多くあります。
症状の経過や周囲の流行状況などからマイコプラズマ感染を強く疑う場合には、検査をせずに治療を行ったり、検査で陰性の結果であっても治療を行う場合もあります。
マイコプラズマは気管支や肺で増殖して、肺炎をおこします。咽頭をぬぐって検体をとる場合、菌が喀痰とともに気管支から咽頭付近まで排出されてこないと、検査で検出することができません。つまり、感染していたとしても、必ずしも検査で検出されるわけではなく、マイコプラズマ感染症の診断は難しいケースが多くあります。
症状の経過や周囲の流行状況などからマイコプラズマ感染を強く疑う場合には、検査をせずに治療を行ったり、検査で陰性の結果であっても治療を行う場合もあります。
治療
マイコプラズマ肺炎では、「マクロライド系抗菌薬」や「キノロン系、テトラサイクリン系抗菌薬」といった、少し特殊な抗菌薬が使用されます。特にマクロライド系の抗菌薬が効かないマイコプラズマの報告もあり、症状や経過などから抗菌薬を慎重に選択します。
また、そのほかにも咳止めや解熱剤などそれぞれの症状を和らげるための薬物療法も行われます。さらに、呼吸困難や脱水などの症状が強いときは、酸素投与や点滴が必要となります。その場合には、入院加療ができる総合病院をご紹介させていただきます。
また、そのほかにも咳止めや解熱剤などそれぞれの症状を和らげるための薬物療法も行われます。さらに、呼吸困難や脱水などの症状が強いときは、酸素投与や点滴が必要となります。その場合には、入院加療ができる総合病院をご紹介させていただきます。
出席停止・通勤停止について
マイコプラズマ感染症は、明確な登園登校停止の期間は定められていません。ただし、熱がある場合や、熱はなくても咳がひどくて睡眠や食事に影響があるような場合には、お休みいただく必要があります。熱が下がり、咳が落ち着いてから登園登校をしてください。咳が残る場合には、できるだけマスクを着用しましょう。
予防
マイコプラズマ感染を防ぐ有効な方法はありません。現在日本ではワクチンもありません。飛沫感染、接触感染で広がるため、基本的な手洗いやうがい、咳エチケットを日頃から心がけるようにしてください。